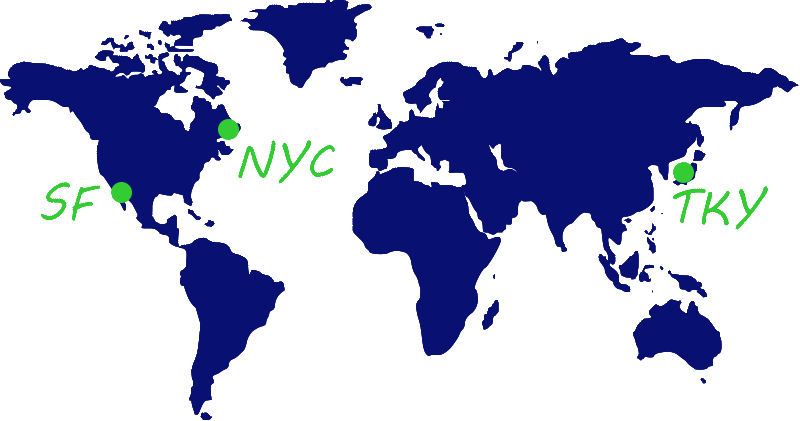
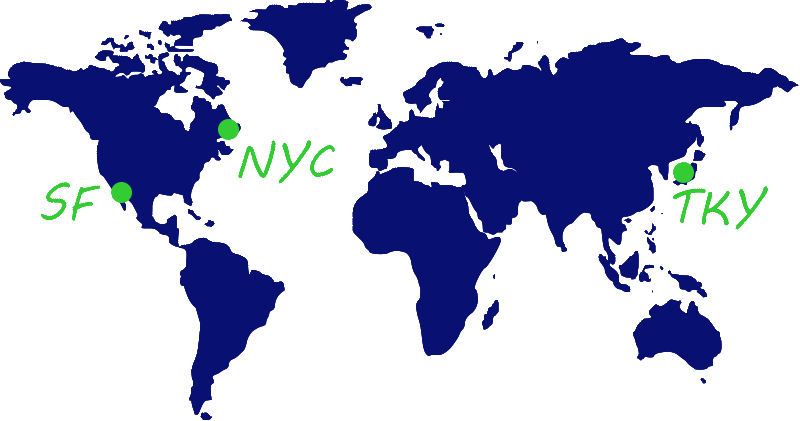
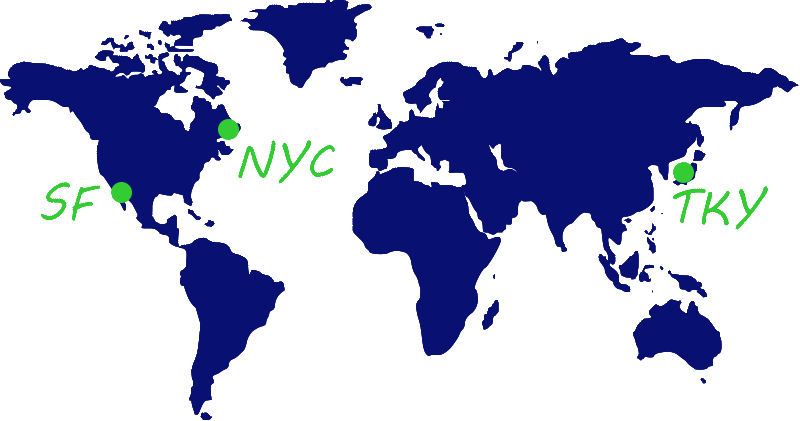

質問−1:従業員50人程度のベンチャー企業で設立5年になります。企業としてアメリカへビジネス進出を考えていますが可能でしょうか。
企業としてアメリカへ事業進出する場合、基本的にはアメリカでの会社設立(子会社や駐在員事務所など)を考えることになり、設立することで、その会社をビザ受け入れのスポンサーとして日本から駐在員を派遣することができます。L-1ビザやEビザ多く使われますが、それぞれに会社条件、ビザ受益者に対する条件がありますので、詳しくはL-1ビザやEビザの説明をご覧ください。
質問−2:アメリカで起業する上でどのようなビジネス形態がありますか?またビザを申請する上で、会社設立時点で注意しておくことはありますか?
代表的な会社形態として、個人経営(Sole Proprietorship)、パートナーシップ(Partnership)、リミテッドパートナーシップ(LP)、株式会社(Business Corporation (Inc./Co./PC) – C CorporationやS Corporationなど)、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)、駐在員事務所(Rep Office)、日本法人の支店(Branch Office)、リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(LLP)があります。ビザ申請で見られる多くの会社形態は株式会社やリミテッド・ライアビリティ・カンパニーで、駐在員事務所もケースとしてはあります。会社の規模やビジネスの種類等によってよりベストな会社形態を選ぶことが重要で、税務上のことなど、会計士に相談してもよろしいでしょう。ビザ申請の際は、ビザの種類によって、日米間の会社関係を示す資料、日本からの出資金の流れやその金額を示す必要性もあり、また設立の証拠など、様々な資料が求められますので、会社設立時点からビザ申請のことも意識して移民弁護士等に相談しながら計画的に会社設立を進めることをお勧めします。
質問−3:当社はアメリカに子会社があるのですが、今後定期的に研修目的で日本からアメリカ子会社に派遣をしたいと考えています。そのようなスキーム作りは可能でしょうか?
代表的なトレーニングビザにはH-3ビザ (職業トレーニングビザ)とJ-1ビザ(交換研修者ビザ)があります。H-3ビザ取得は、最終的な目標が技能習得であり、そのトレーニング事体が雇用主に対して生産的な雇用となってはなりません。最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ないトレーニングであることなど様々な条件があります。一方、J-1ビザは国務省が承認しているプログラムに基づいて発行されるビザで、トレーニングビザの一つとしてOJT(On The Job Training)を基にしたトレーニングも可能となります。有効期間は最長18ヶ月です。どちらのトレーニングビザもしっかりとしたトレーニングプログラムを作成することは重要で、特にJ-1の場合は、英語の環境でトレーニングを受けることが基本となっているため、研修者の英語力も重要となります。
質問−4:当社はアメリカに子会社があり、現在日本人駐在員のみで現地採用はありません。今後、更に日本から駐在員を派遣予定ですが、何か問題はありますでしょうか?
アメリカの会社が日本人ばかりで構成されることは好ましくありません。とりわけ、は申請フォームに従業員構成を示す設問もあります。アメリカ政府はアメリカ市民やアメリカ永住権保持者など現地採用の雇用状況も確認することでしょう。同様にL-1ビザでも注意が必要かもしれません。厳密に全体の何%まで、との明確な指標はありませんが、ビザ申請の際、担当移民弁護士とも相談することをお勧めします。
質問−5:当社は既にアメリカとの間に貿易があります。貿易に基づくビザがあると聞きました。その貿易実績をもとに日本から駐在員の派遣は可能でしょうか?
貿易に基づくビザにはE-1ビザがあります。日米間の貿易が会社の全貿易の50%以上であり、一定期間(少なくとも半年以上)における相当額の継続的な貿易実績を立証できれば、可能性があるかもしれません。一般にはアメリカに駐在員事務所を設立することで、日本の会社の貿易実績を使える可能性が出てくる場合もあります。もちろんビザ受益者の専門性や管理職としての実績など、アメリカでの予定雇内容も含め申請条件の確認も必要です。状況が見合えば、E-1ビザに限らず、E-2ビザやL-1ビザ等々も選択肢になるかもしれません。
質問−6:Lビザ(ブランケット、または個別申請)での会社のオーナーシップ(持分)について詳しく教えてください。
親会社やオーナーが、会社の持分の50%以上を有している必要があります。米国移民局は、50/50のジョイントベンチャーの場合もいずれかのパートナーが拒否権を持たない限り、L-1目的のために適格であると認めています。
また、社長や取締役の国籍が、会社のオーナーシップの国籍と異なっていても、問題ありません。
質問−7:通常、アメリカへ派遣する従業員の非移民ビザ(H-1B、L-1、Eビザなど)のスポンサーになるためにはアメリカに会社が必要と理解していますが、会社設立の予定はありません。それでもアメリカに従業員を派遣したいのですが、何か方法はありませんか?
ご理解の通り、それら非移民ビザ取得にはアメリカにスポンサーとなる会社が必要ですが、ビザ受益者のアメリカ国内の活動内容によって、また特定の条件のもと、日本の会社の代表としてBビザにて従業員をアメリカに派遣できる場合があります。その場合、アメリカに子会社など会社がなくても大丈夫です。中でもB-1 in lieu of H-1BというB-1ビザについてはH-1B保持者と同等の職務に就くことも可能な場合がありますので便利です(一定の取得条件あり)。ただアメリカを源泉として給与を得ることはできません。アメリカにて可能な活動内容の確認は非常に重要ですので、詳しくは専門の弁護士に相談ください。
質問−8:現在、アメリカに駐在員事務所があり、すでに一人L-1ビザにて就労しています。会社としてLブランケットは持っていません。近く、駐在員事務所から現地法人に変更予定ですが、すでに取得しているL-1ビザに影響はありますか?L-1従業員の業務内容に一切の変更はありません。
この場合、業務内容に変更はなくとも、移民局に対して転職申請が必要です。現地法人を新規に設立するということで、厳密にはスポンサー会社が変わるためです。注意点の一つが、継続的に就労を続けるためには、駐在員事務所はすぐに閉鎖せずに、駐在員事務所の閉鎖については、新しい現地法人が設立され、L-1従業員の移民局への転職申請及び認可を受けた後に行うべきでしょう。申請のタイミング等も含め、詳しくは専門の弁護士に相談いただくことをお勧めします。
質問−9:L-1A申請において、米国外にいる人員を部下とみなすことはできるでしょうか?
例えば設立間もない会社で、米国での人員採用がまだできていない場合に、米国オフィスや管理職を米国外の国からサポートする人員を暫定的に部下と見なすことはできますが、正式に部下とみなされるのは、米国ビザ申請会社に雇用されていて米国内で勤務している人になります。
質問−10:弊社(日本)にはアメリカ駐在員事務所や子会社はありません。Bビザ以外に何か日本から日本人従業員を派遣できる方法はありますか?
就労ビザのためにはやはりスポンサーとなる会社がアメリカには必要になります。ただ、派遣する従業員のアメリカでの活動内容や従業員の履歴によってはB-1 in lieu of H-1Bというオプションも検討して良いかもしれません。詳しくは弁護士や専門家に相談されることをお勧めします。